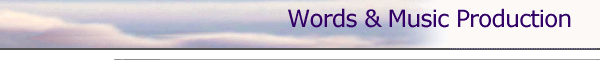| �L���̎v���o |
|
| �w������A�x�݂�����Ƃ悭�R�o����������A���Z��N�̎��̎v���o�̏ꏊ�̂ЂƂɖL���x������A���̎R���ɂ���L���́A���Ђ�����x�s���Ă݂����Ǝv���Ă����ꏊ�������B
���H�A�ӂƎv�������A�������y�����Ă��钇�Ԃɐ��������A�����҂͂R���A���v�S���ŖL���Ɍ��������B
���O�Ƀl�b�g�Œ��ׂ��Ƃ���A�����������������A�������Љ��Ă����B
���Z����u�n���v�ƋL������Ă����͂����A�ό������Ȃ̂��u�n�[�g�`�������v�Ƃ���B�܂��A�����̋C�������Ƃ炦��Ȃ�n�����n�[�g�`�A�u�����ɃJ�b�v���������ƈ������Ȃ�����v�E�E�E�A�܂��킩��Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B
�Ƃ�����A��N�̂X���A�S���Łu�䂪���������L���v�Ɍ��������B
�����́A�F���o�v����Ƃ������ƂŁA�蕨�͌������Ȃ������B���ꂪ���ɂ������̂ŁA�蕨�A�����Ė�����̏ꍇ���l���Ă̕���H���p�ӂ��ē������}�����B
�����Ȃ��b�A�����ƂƂ��ɁA�ɂ��₩�Ȏԓ��̋�C�ƂƂ��Ɍ��n�����B�\�z�ȏ�̐Â����B�����Ȃ��A�������̖�������������ȊO�́A�H���}������X�̂ɂ������ӂ�ɗ������߂Ă����B
���Z����A���������A�x�[�X�L�����v�ɂ��Ă����L���ɖ߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��܂܁A���قɋA�炴��Ȃ������ꂢ�L���E�E�E�B
���̌��A���̓��ƕς��Ȃ��p���������B
�����A�����x�[�X�L�����v�����ꏊ�ɒ������B����̕��i���f���o�����̂悤�ȌΖʁA��������ƌ��߂��N�����A�e���g�����킸������̕��R�ȏꏊ�Ƃ��̋߂��̖ؗ��E�E�E�A�����Ɖ����ς���Ă��Ȃ����i�Ɏv�������炵�A�Â��ȌΖʂ����߂Ă����B
�����A���s�̂R�l�̏����͂���ȏꏊ�͏��߂Ă������炵���u����A���H�v�u�킠�A�������H�v�Ƃ̂͂��Ⴌ�悤�E�E�E�B
�v���o���A�����͂T�l�Ŕ��ق����s��ԂŎ����Ɍ������A�r����x��芷�����l���ցB���̌�͕��������A�y��ŃL�����v���Ă���A�����A�J�̒�������A�[���L���ɂ��ǂ蒅�����̂������B
�����ė����A�L�����v�ɂQ�l�c���A�R�l�ŖL���x��ڎw�����B�J�̍~�钆�A�܂�Ŏ��E�̂����Ȃ��o�R�������B�v������莞�Ԃ�������A���Ԃ̃��X�����߂����Ƒ�����������̂́A��͎v��ʕ����Ɏ֍s���A�s����������́A�������H�ɖʂ����R�������B���ʂɍr�ꋶ���������m�B�݂��̘b�����������ł����������Ȃ��B�u�����A����͂����o����Ă��邩���E�E�E�v����Ȏv���̒��A�R������邵�����Ȃ������B�S�E�S�E�ƍ����C��̎Ζʂ��A�J�V�̒��������v���o���������B
����Ȏv���Ƃ͗����ɁA��N�K�ꂽ�����L���́A���Ƃ��Â��Ɍ}���Ă��ꂽ�B�������Ă��ꂽ�̂͂R�l�̏����B�����́A�u�����ɂ͗D�����Ȃ̂��H�v�Ǝv���Ȃ�����A��͂�A�l�m��ʔ鋫�ł����ė~�����Ɗ�킸�ɂ͂����Ȃ������B
  |
|
|
| |
| �����҂ɂȂ����M�����u���[�i�F�l�l���̂��Ɓj |
|
| �����O�A�F�l�̃z�[���y�[�W�ɂ������G�b�Z�C��ǂ݁A����ɑ��Ĕ�]�������������̂����A�u�ӂނӂ�
�A�������Ƃ��E�E�E�v�̌�ɁA�u���܂ɂ͐V�����G�b�Z�C��������ǂ��Ȃ́H�v�Ȃǂƌ����Ă��܂����B
����������̂������͂Ȃ��B�����������A���������Ă��Ȃ������̂����炵�āE�E�E�B
�Ƃ������ƂŁA�v�X�ɏ����Ă݂邱�Ƃɂ����B
�킯�����đ�w���P�N�x�w�������Ƃ͑O�ɏ��������A��w�ɕ��A���Ă݂�ƁA���R�ɂ�
���Z����A��x�����N���X�������e�����̃N���X�ɂ����B��Q���ē������̂��Ƃ����B
�u�₠�A���R���Ȃ��A�m���Ă�炪�����ėǂ�������v
���������āA�ق��Ƃ������������ƁA
�u������l�����A���Z����̓������|�v
�Ƃe���A�\�����̃N���X���C�g��U��Ԃ��Č����B�������A�ǂ̊�ɂ����o���͂Ȃ������B
�u�m��Ȃ���A���E�E�E�A�N�ȂH�v
�u�������A�l���Ă����A�����ĂȂ����H�v
�u�����E�E�E�v
���̂Ƃ��ɉ�����l�́A�Ȃ�Ƃ��Ƃꂭ�������ȏ����ׂĂ����̂������Ă��邪�A���t��
���킷���Ƃ͂Ȃ������B
�����A���C�����ŁA��l�������ȁA����Ȉ�ۂ������c���Ă����B
���ꂩ��Ԃ��Ȃ����āA������̌ߌ�A�w�Z�Ɋ���o���Ă݂�ƁA
�u�����A�����͋x�u�����Ă�B�������������̂ɂ��v
�u�搶�A��������ŐQ�Ă�Ȃ��̂��v
�ȂǂƁA���傪��ь����Ă����B���ɂ��Ă݂�A
�|��������Ȃ��́A�A�p�[�g�ł�����Q���肷�邩�E�E�E�A����Ƃ��E�E�E�|
�ȂǂƎv���A�A�낤�Ƃ���ƁA
�u�����A�������Ȃ����H��l����Ȃ���v
�ƁA�e���U���Ă����B�ɂԂ��ɂ͑ł��Ă��̃Q�[���ł���B
�����āA��w�߂��̐����ց|�B
�����o�[�ɂ́A���Z�������������Ƃ����l��������Ă����B
�����̎荇�킹�A��������߂Ẵ����o�[�ƂȂ�ƁA��͂�ŏ��ْ͋�����B
���ꂼ��A�ǂ�Ȗ�����ł̂��E�E�E�B�y���݂ł�����B���i�����̑ł����ł킩���Ă���B
�e�́A�U�荞�ނƔM���Ȃ�A������ɏo��B������l�́A������Ǝ�C�B���C�ɏo���
�����~��Ă��܂��B
�������A������l�̂l�́A�ŏ�������Ƃ��̈�ۂƂ͈Ⴂ�A�͋����ł����ŏ�������S���Ă���B
�������˂苭���A�]���̂��Ƃ��Ȃ��Ǝ����̎�𓊂��o���Ȃ��B
���́A�O��I�ɂl�������}�[�N�����B�l�����[�`����������A�U�荞�܂Ȃ��悤�Ɉ��S�p�C��S����
�A���������[�`��������Ƃ��́A�l�̎��ǂ݂Ȃ��珟���ɏo���B
���ǂ܂ꂻ���ȂƂ��́A�_�}�e�������ߍ��݁A�l����o�Ă���̂�҂����B
�ߌォ��̋x�u�ŁA�����킢�ɂȂ�Ƃ���A
�͂̍����ŏI�I�ɏ��������߂�B
���X�l�Ɩڂ������B�ނ��������̏o���ɋC�t���n�߂��悤�������B
�����܂ł��Ȃ��A���̂����l����������}�[�N���n�߂��B
���ʂ͂ǂ����������E�E�E�A�͂����肵���L���͂Ȃ����A���Ԃ�E�E�E�A
�l���������������悤�Ɏv���B���ꂪ�l�Ǝ��̕t�������̎n�܂肾�����B
���ꂩ��Ƃ������́A�����A�ԎD�A�J�[�h�Q�[���A���n�E�E�E�A�Ȃɂ�����ƈꏏ�ɍs�������B
�M�����u���w����l�g�̒a���ł������B
�������A�ނ̖��_�̂��߂Ɉꌾ�t�������Ă������A
�ނ͎��ƈ���āA��w�̃[�~�����Ȃ��邱�ƂȂ��A���ꂱ���A�D�G�Ȑ��тő��Ƃ����B
���ƌ�A�l�̋Ζ��n�̊W�ŁA��@������Ȃ��Ȃ�A���ł͔N���̂����
����ɂȂ��Ă��܂������A�����ς��ʗǂ��F�l�ł���B
����ɂ��Ă��A�l�Ԃ̐��i�Ƃ����̂́A���������ς��Ȃ����̂炵���B
���̂˂苭���l���A����l�����A���I�@�ւ̌����҂Ƃ��āA�\�]�N���������錤���A
�S���I�Ȍ�������Ŗ��_����܂����Ƃ����B�F�l�̎��Ƃ��ẮA�Ȃ�Ƃ��������b�ł������B
�����������[���Łu���߂łƂ��v�������ƁA�u���͈���ŋA��A���C����オ���Ăǂ��́E�E�v�ƁB
�e���Ȃ̂��A�������܂��l�炵���B�ԐM���[���ŁA�u�g�̂ɂ͏[���C�������A
���₨�݂��l�����ǂȁE�E�E�v�A�ȂǂƁ|�B
�������A�Ō�Ɉꌾ�����Ă��������B�l���Ɂ|�B
�u�N�����̏܂���ꂽ�̂́A���̂˂苭������ł����̂́A���Ƃ������C�o���A
�����āA�M�����u���̎t����������ł͂Ȃ��̂��H�I�v�ƁB
�l���ɂ��ẮA�܂��܂��G�s�\�[�h������̂����A����͂܂����̋@��ɂ��Ă������B
�ނ��A����Ȃ錤���ɐ�O�ł��Ȃ��Ȃ�ƍ��邩��|�B
|
|
|
| |
| �t�e�n�ɑ����������̓��E�E�E |
|
| �����Q�O�N�ȏ�O�̘b�ł���B
���͂t�e�n�ɑ��������E�E�E�A�炵���E�E�E�B
����ȁA����߂ĞB���Ȍ�����������̂́A���ꂪ���̒����������炾�B
�|�Ȃ��A�����|
���������O�ɂ�����ƕ����Ăق����B
����́E�E�E�A�܂��t�e�n�ɂ��Ă̎s�̖{�͏��Ȃ��A�܂��ăe���r�̓��ԂȂǂ́A
�قƂ�ǂȂ����ゾ�����Ǝv���B
���́A�ǂ����킩��Ȃ��������A��̑���������Ă����B
���̎��A�w��̋�Ɍ��������A�Ȃ�ƂȂ��s���ɋ���Ď��͑���o�����B
�������܂ő��������A���̌����߂Â��Ă��Ă���̂��킩��A ���͐g���B���悤�ɁA���̏�ɕ������ɂȂ����B
����ƁA����͎��̐^��Ŏ~�܂����B
�����Ƃ��Ă���ƁA�����Ɍ������˂���A���͂̑����^�������N�₩�ȗΐF�ɋP�����B
���̏u�ԁA���̈ӎ��͉��̂��Ă����B
�����āA�����K�N�K�N�����A�����͂Ȃ������ɂ��炦����Ȃ��k���Ƌ��ɖڂ��o�߂��B
���������Ǝv���A�������A���|���͏����Ȃ������B���v������ƁA���̂S�������������B
���ꂾ���Ȃ�A�m���ɁA
�|�Ȃ��A�����E�E�E�|
����ŏI���͂��������B
�����A����Ȗ����������̌ߑO���A���͗F�l�̈�l�ɂ��̘b�����Ă����B
�ނ́A�ڂɌ�������̂����M���Ȃ��A����Ȓj����������A
�u���܂��A�ςȖ{�����ǂ�ł邩��A����Ȗ��A�����v
�ƁA���̘b����ɕ����Ă����B
�����āE�E�E�A���̓��̗[���A�������ŗ[����ǂ�ł������̗F�l���A
�u�����A�����A���܂��A���̖������̉������������v
�ƁA�ˑR�����Ă����B���Ȃ�^���Ȗʂ����ł������B
�u�m���E�E�E�A�ڂ��o�߂��̂�4�������������Ǝv�����ǁE�E�E�v
�u�z���g��?�v
�Ԃ��̔ނ̊炪�A�������߂Č������̂́A���̋C�̂����������낤���B
�ނ́A�ق��ė[�����J�����܂܁A�����ȋL�����w�����Ȃ���n���Ă��ꂽ�B
�����ɂ́A�u�t�e�n��?�v�Ƃ������o���̌�ɁA
�|�����A�S�������A�D�y��〈��Ō��镨�̂���ы���̂��ڌ�����E�E�E�|
�Ƒ����Ă����B
���̗F�l�͂���܂ł̑ԓx����ς����A
�u�C�������ȁA���Ɋ��Ȃ�v
�Ȃǂƌ����n�߂��B
������������͎̂��̕��ŁA
�|�܂��A���̒��̂��Ƃ�����E�E�E�|
�Ǝv���Ă����̂��A�Ȃɂ�猻�����������Ă��Ă����B
���ꂩ����A�m���ł͂Ȃ��������A����Ȗ������Ă����悤�ȋC������B
�����āE�E�E�A����́A�P�T�N�قǑO�̂��ƁE�E�E�B
�钆�̂Q���߂��܂Ŏd�������Ă��āA�O�̋�C���z�����ƁA�}���V�����̗x���łӂƑ����~�߁A
���̊O�������Ƃ��̂��Ƃł������B
���̏��ɁA�I�����W�F�̌����������B�����낤�ƌ��Ă���ƁA���̌����l�������Ɍ��̋ʂ��A
���S���牓�̂������Ǝv���ƁA�ЂƂӂ��ƁA�܂����S�ɖ߂�A�Ăт����𗣂ꓮ���o���B ���͂��炭��R�Ƃ���߂Ă������A
�����ɂƂ��ĕԂ��A�r�f�I�J�����������Ă����B
�������A�]������ĂĂ����̂��낤�B�o�b�e���[���Ȃ������B
�܂������ɖ߂�A
�u�o�b�e���[�A�o�b�e���[�E�E�E�A�o�b�e���[�͉������v
�ƂԂ₫�Ȃ���A�悤�₭����������A�Z�b�g���Ė߂�̂ɂT���ȏ�͂������Ă����B
���Ɋ��A���̋���������A�������̌��͏����Ă����B
���̂܂ܑ҂��ƂR�O���B�������E�E�E�A����͍Ăь���邱�Ƃ͂Ȃ������B
�܂��A���b���Ƃ����l�����邾�낤���A�v���Y�}���ۂƂ����l�����邾�낤�B
����͂����Ƃ��āA���������āA���Ɠ����悤�Ȍo���������l��������E�E�E�B
�����ɁA�������E�E�E�B
���m�̐��E�̐l�ɂ́A���ꂮ����C�Â���Ȃ��悤�ɁE�E�E�B
|
|
|
|
| |
| �e�B�[���Y�N���[�̐��݂̐e�H(�g���̂���) |
|
| �P�O�N�߂��O�̘b�ɂȂ邪�A��������ǂ̃v���f���[�T�[�g���ɌĂяo���ꂽ�B
�����g���[�h�}�[�N�̖X�q�����Ԃ�A���R�[�h��܂̐R���������Ă����l�ŁA�ƊE�ł͂�����ƒm��ꂽ���݂ł͂��������A���͓�������e���݂������Ă�����l�ł������B
�����A�o�����Ă݂�ƁA��܂�̃C�x���g�ɁA�M�c�~�q�Ǝq���B��g�ݍ��킹�ē��w�𒆐S�ɂ����X�e�[�W������Ă݂Ȃ����A�Ƃ����b�ł������B
�m���ɁA�M�c�̃t�@���Z�b�g�͓�����������A���w�Ɍ����Ă͂����B
�������ɖ߂��Ă���ޏ��ɘA�����Ă݂��B
�u���w�ł����H�v
�u�����A���w�E�E�E�v
�u�q���B�́H�v
�u�����A����ɂ��ẮE�E�E�v
�\���ʼn̂��Ă����ޏ��ɂ͐Q���ɐ��̘b�ŁA���܂��Ɏ��ԓI�ȗ]�T�͂Ȃ������B�������A���܂���C�łȂ��ޏ�������A�����āA�g���Ɏq���B�̂��Ƃ��m�F����ƁA
�u����A�S������̎��������c�ɂ����Ă݂����A������ȂB�������Ŏ�z���Ă���Ȃ����v
�|��z�������āA�ٓ�����Ȃ�����A����ȁA�����ɂ́E�E�E�|
�ȂǂƎv���A�m�荇���̏��w�Z�̐搶�ɖ₢���킹�Ă݂���A
�u�킩��܂����B����Ă݂܂��傤�v
�Ƃ����b�ŁA�}篁A���̊w�Z�̎q�����܂߂ăI�[�f�B�V���������邱�ƂɂȂ����B
�����o�[�����܂�A�A���̗��K�̐��ʂ������āA�X�e�[�W�͑�D�]�ł������B
���ꂪ�A���݂̃e�B�[���Y�N���[�̎n�܂�ł���B
���̌�A�q���B�̓����o�[������ւ��A�I���W�i���Ȓ��S�̃O���[�v�ɐ��������B�J�o�[�Ȃ͓��w����A�r�[�g���Y��J�[�y���^�[�Y�Ȃǂ̉̂ɂȂ�A�M�c�̎w���̂������ŁA���ꂢ�ȃn�[���j�[�����o����悤�ɂȂ����B�I���W�i���Ȃ����������A��������̋Ȃ��܂߂�ƂT�O�Ȃ͉���Ȃ����낤�B
�P��̃C�x���g�ŏI���͂��������O���[�v�����U���Ȃ������̂́A�g���̊��߂�����A�܂��A�����g�A�q���B�̋z���͂����炽�߂Ċ����A������Ă邱�Ƃɖ��͂����������炩������Ȃ��B
�U��Ԃ��Ă݂�ƁA�����������āA�ǂ����悤���Ȃ��A�Ǝv���Ă����q���������ă��C�����̂���悤�ɂȂ�����A���\��ł����q���C�L�C�L�Ǝ�����\���ł���悤�ɂȂ�����A�����o�[�̐����͊y���݂ł������B
������A�ꉞ�I�[�f�B�V�����͂���̂����A�Ȃ�ׂ���͍L���J���Ă������Ǝv���B
�����A���͌��t�����A��V�A�}�i�[�ɂ��Ă͂��邳���������A�`�[�����[�N���厖�ɂ��Ă�����肾�B
����Ȃ��ƂŁA���Ԃ�A�̂���肭�Ȃ肽�������Ȃ�A�e�B�[���Y�N���[�͋��S�n�̂����ꏊ�ł͂Ȃ��̂�������Ȃ��B
�t�ɁA���C�ƃZ���X���������Ă���A�L�тĂ�����O���[�v�ł�����B
�����āA�����o�[�ɖ]�ނ��Ƃ́A���y��ʂ��Ă��낢��Ȃ��Ƃ��w�сA�ڕW�������ɒu���āA���X�w�͂��Ă����Ăق����Ɗ���Ă���B
�b�͕�����ς��Ă��܂������A���̂g���̊��߂��Ȃ�������A�����炭�A�e�B�[���Y�N���[�Ƃ����O���[�v�͐��܂�Ȃ��������낤�Ǝv���B
����Ȃ��Ƃ���A�O���[�v�̐��݂̐e�Ƃ������ׂ��l���Љ�Ă݂��B
|
|
|
| |
| �j�͖ق��āE�E�E(�݂��{�[�g���̎�l�̂���) |
|
| ���ق̌ܗŊs�����Ƃ����A���Ԃ�A���ق��ό��ŖK�ꂽ�l�͒m���Ă���Ǝv�����A���̐��`�̖x������ł���݂��{�[�g�������邱�Ƃ͒m���Ă��邾�낤���B
�������邩�ǂ����͒肩�ł͂Ȃ����A�����������̍��́A�悭����ɏ�������̂������B�m���E�E�E�A�S�T���łQ�O�O�~���A�R�O�O�~���������E�E�E�B
���̎��Ԃ́A������葆���ƁA���傤�ǖx��������鎞�Ԃɑ�������炵�������B
�������A���������������́A�F�B�ƍs���ƁA�����Ă��͋�������`�ɂȂ��Ă��܂��A��ɓ��h���o���A���ɂ͂��ꂪ�j��Ă��܂��قǂ������B
����ł��A���������������̂ɂR�O���߂��������Ă��܂��A�Q������ƁA�݂��{�[�g���̗����x�����ɂ����A�c��̔N�߂ɋ߂�������ɁA
�u�P�T�����߂���v
�Ȃǂƌ����A������̒��ߗ��������ꂽ�B
�����A���Z����ɂȂ�Ɗ�Ȃ��݂ɂȂ�A��l�ł��s���悤�ɂȂ��Ă���́A
�u���ԉ߂��Ă邯�ǂ�����v
�ƁA�܂��Ă����悤�ɂȂ����B
�N�����l�̂��Ȃ����J�̓��Ƃ��A���Ƃ������I������肵���Ƃ��A�F�l�ƕʂ�Ă����l�ōs�����肵�����̂�����A���ɂ́A
�u�����w�Z�I������̂����v
�ƁA�Ί�������Ă���邱�Ƃ��������B
�����A��A�ɂȂ��Ă�����A���̃{�[�g���̎�l�A���Ԃ�A������̂���l�������Ǝv�����A�N�ɑ��Ă����z���Ȃ������B
�قƂ�ǖ����ŁA�{�[�g�����t������Ƃ������A
�u�����Ƃ��������A�E���A�E�v
�ƁA�{�����悤�Ȑ��ŁA�Ⴍ�������x�������B
�����āA����͉Ă̏I��肾�����Ǝv���B
�w�Z�̕��Ɍ��C�������A�搶�Ƃ���㒅���������̂��Ƃ������B
�s�d�̔����ꂽ���K���X�ɁA���łɐ��H������Ă������A���͌ܗŊs�̓d��ō~��A�����̕��Ɍ������ĕ����n�߂Ă����B
���R�A���͗�݂̑��{�[�g���̕��Ɍ������Ă����B
�J�͖{�~��ɂȂ��Ă��āA�{�[�g�ɂ͂��łɔ����r�j�[���V�[�g���|�����Ă����B
�������ɍs���ƁA������̎p�͂Ȃ��A�������X�I��������Ƃ���ł������B
���̊������ƕ|����ŁA����ł��A
�u���̂����v
�ƁA���t���|���Ă��ꂽ�B
���͊�{�������A�O�ɏo���B
�J���͕ς��Ȃ��������A�ނ͖����ł����Ƃ͈Ⴄ�A�傫�߂̃{�[�g�̃V�[�g����苎��A
�u����̕��́E�E�E�v
�ƌ��������A���t��������B
���͂��̂܂��A�J�̒��𑆂��o�����B
������U�蕥�����̂悤�ɕK���ő������B
�����āE�E�E�B
�����̗���̂�����ł��A�����̃y�[�X�ő����ł����B
���i�́A���X�U��Ԃ��ĕ������C������̂����A���̓��́A���������ł����B
����ƁA�ˑR�{�[�g�������Ȃ��Ȃ����B
�����̒��Ƀ{�[�g�͓˂�����ł����B
�|���܂����|
�Ǝv�������A�{�[�g�͑O�ɂ����ɂ��i�܂Ȃ��B
�J���������Ȃ��Ă����B
���̂����ŁA�����͌�����l�e���܂�łȂ������B�������ĂׂȂ��B
����ꓬ���Ă���ƁA�����̕��ɃG���W���������������B
�ނ��A�����p�̃{�[�g�ŗ��Ă��ꂽ�̂������B
�ނ͐T�d�Ɏ��̃{�[�g�ɋ߂Â��A������̂����͂��݂Ő����̖����A�{�[�g�������̂��m���߂�ƁA
�u���݂܂���v
�Ƃ����A���̌��t�ɖ����ł��Ȃ����ƁA���̏�𗧂��������B
�D������ɖ߂�ƁA�ނ͐m�������Ŏ���҂��Ă����B
�����ă{�[�g����ƁA�������̒��ɓ���A�^�������^�I������n���A�M�����������Ă��ꂽ�B
���͔���@���A�M���Ԓ���������ƁA
�u���݂܂���ł����v
�ƁA������x����������ƁA�ނ͏��߂āA���N�ڂ��ŏ��߂Ă̏Ί�������A
�u�������ǂ��A��������Ȃ�v
���������ƁA�����������݂���ɂ����B
���̌���ނƂ͉��x��������킹�����A�ȑO�̕\��ɖ߂��Ă����B
���́A�V�l�^�ɂӂ��킵�����ǂ����͕ʂɂ��āA�Ȃ�����ۂɎc��l���ł������B
|
|
|
| |
| �l�͌������ɂ�炸�E�E�E(�̂̉��y���Ԃr���̂���) |
|
| ��w���ƌ�A���N����Ћ߂����������������A�����ɂ����y�̏o����������B
�����ۂ́A�r�Ƃ�����y�́A�����ł�����Ə�����A�����Ċዾ�������A�����ɂ��^�ʖڂ����ȃ^�C�v�ŁA���̍�����Ă�����Ђ̂o�q����S�ʓI�Ɏ肪����A���͂ɂ͂�����Ƃ��邳���j�ł������B
�����A���̓����A�ނ͓����q�̃t�@���ł���A���Ȃʼn̂��̂Ƃ����A�����q���O���A�R�̂������̂��A�ӊO�Ƃ����ΈӊO�ł������B
�����āA���Ј�N�ڂ̏H���������E�E�E�B
���̐�y�A�r���������z�����邱�ƂɂȂ�A���̎�`���ɍs�������Ƃ��A�G���L�̖��͂�m�邫�������ɂȂ�Ƃ́A�v�������Ȃ������B
�E��ŏo�����������z���ł��������A��`���܂ł��Ȃ����炢�̏��Ȃ��ו��͂������Ȃ��ЂÂ��A�g���b�N��҂��Ȃ���A�������z���Ă���ƁA
�u���������A�����A�M�^�[��������ȁv
�ނ͂����A�����Ă����B
�r���͎��̗�����(��̗��ɃM�^�[)��ǂ�ł����炵���B
�ނ́A���ɂ������G���L�M�^�[���A���Ɏ�n�����B
��Ɏ���Ă݂�ƁA���̃M�^�[�ɂ͔ނ̃T�C�������Ă������B
�{��ǂ�A�����������肷��p�������Ă��Ȃ����ɂ́A���ƂȂ��A�~�X�}�b�`�Ɏv���Ă����̂������B
�|�ւ����A����ϐ�y�̃M�^�[�������̂��|
�Ǝv���A�������ɂ����B
���߂Ď�ɂ����G���L�́A�d���āA��������Ȃ��āA�Ȃ�ƂȂ������ɂ��������������B
�d���Ȃ��A���������������Ԃł����������B
�u�����e���Ă݂��v
�|�Ȃɂ��������āE�E�E�|
�����Ԃ������A�I���W�i���Ȃ̃R�[�h��K���ɒe���Ă����B
�u�����A�e����ȁB������Ƒ݂��Ă݂ȁv
�ނ͂��������ƁA�s�b�N����ɂ��A�������Ɋ��Ȃ��@�q�Ȏ���ŁA�y�₩�Ɍ���e���n�߂��B
�|����́A�������E�E�E�A�x���`���[�Y�́E�E�E�A�����ƁE�E�E�|
�����l���Ă���ƁA
�u�Ƃ���Ŋ����A����Ȃӂ��ɒe���Ȃ����ȁv
���������ƁA�s�b�N���g���ĒP����e���͂��߂��B�Ȃꂽ����ł���B
��{�I�ɂ̓R�[�h�̍�����e���A���X�t�H�[�N�Ŏg���ቹ�̂Ȃ������Ă����B
���Ƃ��o�������������B
�u�R�[�h�������Ă��炦�܂����v
���������ƁA�ނ͗]���Ă����i�{�[�����̐�[�ɁA���̋Ȃ��͂킩��Ȃ��������A�R�[�h����������ł��ꂽ�B���͂r���̒e�������Y���ŁA�����𒆐S�ɓK���ɒe���Ă݂��B����ƁA
�u�����A���܂��x�[�X����v
�ƁA�ˑR�^��ɂȂ����B
�u�x�[�X
?
�v
�u�������A�G���L�̃x�[�X����v
�u��������ƂȂ��ł���A�l�̓t�H�[�N���������A�G���L�Ȃ�āE�E�E�v
�u���v����A���܂��Ȃ����B���͂����A���x�[�X���Ȃ���v
�b���ƁA�ނ���Ђőg��ł����o���h�ŁA�x�[�X�����l�Ԃ��]�ɂȂ��āA�����o�[������Ȃ��Ƃ������Ƃ������B
����Ȃ���ȂŁA���̓G���L�x�[�X����ɂ��邱�ƂɂȂ�A�ЂƂA�V�������E�ɓ��邱�ƂƂȂ����B
���̌o���́A�����ƍ��ł��A���y�����ɂ�����A�ǂ����ɐ����Ă���̂��낤�Ǝv���B
�������E�E�E�A�ƍ��ł��v���B���́A�R�̍D���ŁA�����q���O�ɗ܂���r�����A�ؗ�ɃG���L�M�^�[��e�����Ȃ��Ƃ́E�E�E�B
�l�͌������ɂ��Ȃ����̂ł���B
�@
|
|
|
| |
| �����炵�����y ? (�f�B���N�^�[�E�̂s���̂���) |
|
| �@���̐l�Ƃ̂������́A�܂��d�b����n�܂����B
�u���T�D�y�̕��ɍs�����ǁA��܂����ˁv
�u�����A���Ԃ͂Ƃ�܂��A���ł��E�E�E�v
�Ȃ�ăR�g�͂Ȃ��A�������͉ɂ����ė]���Ă������A���܂��ɂ��̓����A���đ����Ƀq�b�g�Ȃ��Ƃ��Ă��������背�R�[�h��Ђ̃f�B���N�^�[�̂s������������A���Ƃ��Ă͒f�闝�R�͂Ȃ������B
�����ė��T�A�z�e���̃��r�[�ő҂��Ă���ƁA�����̂����A���X����C���̂R�O�㔼�̒j���߂Â��Ă����B
�����������A��ҁA�s���܂Ȃ����A����Ȓj��z�����Ă������A�����͗D�����������́A���₩�ł̂�т肵�������̐l�ł������B
�u����A���܂��܊�����������Ȃ����ɂ��ĂˁA����ŋ��������������ǂˁv
�����b�A�쎌��Ȃ����Ă݂Ă���A�Ƃ������Ƃł������B�ȂA�����A�ڂ̑O�����邭�Ȃ��������ł������B
���ꂩ�甼�N���܂�A���͋Ȃ������A���X�Ɣނɑ��葱�����B���̂��߂ɏ������Ȃ͂T�O�ȂقǁB�����āA���̒����瑗�����̂͂Q�O���Ȃ��������E�E�E�B�������A
�u�ȂႤ��ˁE�E�E�v
�Ƃs���B
�u�ǂ����Ⴄ��ł���?�v
�ƁA���B
����Ȃ��Ƃ肪�����āA�P�N�߂�������������A�d�b�̌������ŁA
�u���Ⴀ�A�Ƃ肠�����^���Ă݂܂��傤���v
�u�͂��A���肪�Ƃ��������܂��B����ŁA�ǂ̋ȂŁE�E�E�v
�u�����ł��ˁA�P�Ȃ́E�E�E�v
�Ȗ����āA���͌��t�ɋl�܂����B
�u�����P�Ȃ́A��������̘^�肽���̂ł����ł�����v
���R�[�f�B���O�̃X�P�W���[�������܂�A�J���I�P���ł��A�{�[�J�����R�[�f�B���O�̓��ɗ�������߂ɏ㋞�����B
���R�[�f�B���O�����̂͂Q�ȁB
�P�Ȃ͔ނ��I�Ȃ������B
����́A�ŏ��ɁA��ԍŏ��ɁA�ނ����ɋ������������Ȃł������B
�Ƃ������Ƃ́A����ȍ~�̍�i�ɂ������̂��Ȃ������A�Ƃ������f�ł������B
���R�[�f�B���O���I���A�X�^�W�I�߂��̋i���X�ŁA
�u�ǂ��ł����A���R�[�f�B���O�́v
�Ƃs���B
�u�����A�܂��E�E�E�v
���������āA�s�����炯�ł������B�I�Ȃ��A�A�����W���E�E�E�B
������@�����̂��ǂ����A�ނ͂��肰�Ȃ��������B
�u��������A���Ȃ��A�l���C�ɓ���Ȃ���낤�Ƃ��Ă�����Ȃ��́v
�|����Ⴛ���ł���A�����āE�E�E�|
���̌��t���A���͎v�킸���ݍ���ł����B
�����āA���̈Ӗ��𗝉������B
�}���������B
���́A�ނ��C�ɓ���Ȃ���邽�߂ɁA�ނ��f�B���N�^�[�Ƃ��Đ��ɏo������i���A���낢�뒮���Ă����B�����āA���̒��ŁA���Ĕ�Ȃ�Ȃ������Ă����̂��B
�u�l�́A���܂łɂȂ��̂���肽����ˁB�����āA��������ɂ́A���ꂪ�o����Ǝv���Ă邩��E�E�E�B������A�����炵���ȁA�����̊����̂܂܂ɏ����Ăق�����ˁv
���́A�炩��̏o��v���ł������B�����āA�����̕s����p�����B
���ꂩ��܂��Ȃ��A�Ⴍ���Ăs���͑��E���A���R�[�f�B���O�����Ȃ����ɏo�邱�Ƃ͂Ȃ������B
�����A�ނƉ������A���͎����̊�����M���A��i�����������Ă���B
������������A�R���T�[�g�e�[�}�́u�N�炵���v�́A�����Ɍ����Č��������Ă���̂�������Ȃ��B
�@�@ |
|
|
| |
| ������u�����N�������Ă�(�F�l�l���̂���) |
|
| ���̌�F�^�̒��ɁA��w����̗F�l�l�������Ă����Ȃ��ƁA���������B
���̃z�[���y�[�W������Ă��ꂽ��m�ł���B
�ނƉ�����̂́A�k��ŁA���ے��Ɉڂ��Ă���̂��Ƃł������B�����ꏑ�����ƂɂȂ�Ǝv�����A�킯�����ĂP�N�x�w���A�����čĂё�w�̖���������Ă͌������̂́A�����ɂ͐e�����F�l�����Ȃ��������A�܂��A���R�̂��Ƃ��T�{�������ɂȂ��Ă���������A�������u�`�ɏo�Ă̋A�蓹�A
�u�����A�����A���܂��̂Ƃ��A���̋߂��Ȃ̂��v
�U������ƁA�w�̍����A�Ђ����Ƃ����j���������Ɍ������ĕ����Ă��Ă����B
�ዾ���������A�n���T�������₯�ɐ_�o�������Ȋ����̂���A�`���b�g���ȃ^�C�v�̒j���B
�������A�ǂ����Ō������Ƃ��������B
���l����ƁA��������̂͂��A�Q�O�����炸�̓����[�~�̊w�����������A���O�͊o���Ă��Ȃ��B
�u���܂��̂Ƃ��A�`���b�g����Ă����Ă������v
�����Ȃ��炻�������B�C���_�A�Ƃ����킯�ɂ��������A
�u�����E�E�E�v
�ƁA�Ԃ̔������Ԏ��œ�����B
�ނ͈��S�����悤�ɁA�}�ɖ����ɂȂ�B
�G�߂͏H�B�k��a�@�̋�Ǖ��̂����肩��A�k�P�W���܂ŁA�قƂ�ǖ����ŕ������B
�����Ȃ�A���X�̒��ɁA�H�ȂȂ��A�ȂǂƎv���A���̂P�������т����Ȃ͂����A�ނ̐_�o�������ȕ��͋C���A�����ɂ�����Ă����B
�|�Ȃ�̗p�Ȃ낤�|
�ȂǂƎv���A�����̃A�p�[�g�ɒ������B
�����J���A�����ɏ������ꂽ���̂́A����������͂Ȃ�̘b���Ȃ��B
�d���Ȃ��A���e���ȍ��z�c�����߂�B
�`���b�g�������ق̌�A
�u���������A���̎Љ�A�ǂ��v���v
�u�E�E�E�v
���̎���������A�����������ƎR�ς݂����A���̂Ƃ��́A
�|�����A�������������|
�ƁA���C�ɂƂ��Ĕނ̊�����߂Ă����B
�ۂ�ۂ�b���n�߂āA�ނ̌����������Ƃ�����Ƃ킩�����̂́A���P���Ԃ������Ă��炾�����B�v����ɁA�ނ�����Ă���w���^���ɎQ�����Ȃ����Ƃ������U�������̂��B
���̍��́A�w���^�������Ȃ芈�����������ゾ�B
�B���ɓ����Ă��̏�͕ʂꂽ���A���̌�A�ނ͊w���^�����瑫��E�E�E�H�A�����āA�t�������Ă݂�ƁA���Ƃ̓^�C�v����������A�Ȃ��Ȃ��ʔ����j�ŁA�Ȃ����E�}���������B
���ꂩ��R�O�N�߂��A�ނ͎Љ�̈���ƂȂ�A����p�\�R���ɂ͂�����Ƃ��邳���a�m�ƂȂ�A�����V�����ߍ���ł��鎄�̗ǂ��A�h�o�C�U�[�ł���A�ǂ��F�l�ł�����B
�����āA���̑��q���|�\�E�ɓ����Ă���A�ނ̉����X�A�����ł��낢�남���b�ɂȂ��Ă���B
���̊ԁA�N����ŁA�P�O�N����킸�ɂ������A�F�B�Ƃ����͎̂��ɂ������̂ł���B������Ƃ���ɁA�����A���܂��Řb����Ƃ��낪���ɂ����B
������A���q�B�ɂ��A�e�B�[���Y�N���[�̃����o�[�ɂ��A
�u�F�B�͑厖�ɂ��Ȃ�����A��낤�Ǝv���Ă����Ȃ��Ȃ�Ƃ������邩��B�Ƃ��ɁA�w������̗F�B�͈ꐶ������������Ȃ�����v
���M�������āA�����b���Ă���B
����Ȉ����ŁA�ނ͂��̃z�[���y�[�W�ƁA�����āuOPCON
in Sapporo�v�Ƃ����z�[���y�[�W������Ă���Ă���B����ɁA���̂l���̃z�[���y�[�W�����邪�A���̏Љ�͔ނ̗���������Ă���ɂ��悤�B
�ނ��āA����ς�_�o�������E�E�E�A������B |
|